Linux初心者::mintでssh設定にsshdは不要|CPU|スペック|ゴミ箱|メモリ|
linux mintの最初の設定について、初心者の方にお知らせがあります。
数年前に発覚した衝撃の事実ですが。これは凄い大発見です!大事なので先に結論です!
linux mintでのssh設定は「sshd」が不要な場合(古いバージョン)があるというのは知っておくべきかと。
いくら頑張っても出来る訳がなかったのでした。Linuxあるあるですね。
自分はそうとは知らず、大量の時間を失いました。
殆どの解説サイトでも知ることが出来ませんでしたし、これは本を買うべきだった・・と思った理由の一つでした。
(本にも書いてないかも知れませんが)
本文よりも重要な「これだけは知っておきたい」話でした。多分、たくさん解決すると思います。。
目次1: 初期設定linuxのCPU・スペック・メモリを知りたいとき 2: Linuxで、ゴミ箱がない!|設定方法 3: ユーザー名とパスワードの変更ではなく新規作成がしたい 4: linux mintでのssh設定は「sshd不要」だった!と気付いた個人の感想 5: 保護されていない通信を解除する方法 6: Rhythmbox|参考・終わりに |
1: 初期設定linuxのCPU・スペック・メモリを知りたいとき
フリーズすることが多かったので、最初はメモリがどれくらいあるのか気になり、
調べていた覚え書きですが・・いつの間にかcpuなどの確認方法を調べだし。
できれば、windowsの時の元のスペックが分かると良いなとおもったのですが・・
(どんなパソコンだったのか、自分でももう分からないので)
その確認方法を探してみましたが・・
そういえば、windows環境は綺麗に消し去ってしまっていたのでした。
なので、そんなものはありはしない・・。
ターミナルエミュレータ(端末?、あの$や#から始まる、記号を入力する黒いウィンドウ)
で、何回かコピペして調べました。
$ cat /proc/cpuinfo
で、ズラーッと項目と数字などがでてきますが・・
私は以下のことだけで良かったので、
全部は載せませんけど・・
一部のみ、参考例(数字は微妙に変えてあります):
processor : 0
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 6
model : 58
model name : Intel(R) Core(TM) i5-3000M CPU @ 2.60GHz
stepping : 9
microcode : 0x15
cpu MHz : 1199.865
cache size : 3072 KB
physical id : 0
siblings : 4
core id : 0
cpu cores : 2
apicid : 0
initial apicid : 0
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
flags : fpu vme de ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
bugs :
bogomips : 5188.36
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:
私の必要だった情報:
processor は、0〜3の、 4つ(上記の参考例が4つ分、ずら〜っと並んでいました!)
model
name には、知りたかったGHz が表示されていて、2.6GHz
core
id は、3と4それぞれに、1つ X 2つ。
cpu cores は、2 X4つ
↑
このブログは自分の覚え書き用でもあるので、載せています・・。
以下、ちょっと分からないメモ(以下を部分的にコピペで検索すると
LINUXのことしか出てこないので、LINUXの事であるのは確かですが)
↓
メモリ勉強中
Mem:のfree + buffer + cache
= -/+ buffers/cache:のfree
以下のサイト様、お世話になりました・・。
おかげ様でメモリやスペックの確認ができましたので、非常に参考になり感謝申し上げます。ありがとうございました。
2: Linuxで、ゴミ箱がない!|設定方法
今回、気になったことは、
時々なぜか、ゴミ箱がなくなっていたり
ひょっこり出てきたりしている
気がするので、「ゴミ箱の出し方」を
探してみました。
やり方 ↓
メニュー
↓
設定
↓
デスクトップ
↓
デスクトップアイコン
↓
ゴミ箱 ON
↑
これだけで‥、オッケーです‥。
簡単だったので‥記事にするほどのものではないかと思われますが
念の為に覚書をしています。
自分はどうも昔から・・(常日頃から)、忘れっぽいので
同じことを調べたりすることが多いので‥
自分のブログで記事一覧から検察して
出てきたりすることが多々あり、
あとから何か発見をして編集(追記)しようと思って探すと
似たような記事がいくつも出てきたりします。
そういうことすらも数年ぶりだと
すっかり忘れていたりします。
(数ヶ月でも、忘れるときは忘れてますが)
この忘れっぽさがアルツハイマーとか認知症とか
関係ないかと気になりだした・・今日このごろ。
以前より運営していたブログでlinuxに関する記事がポツポツ増えてきていたため、
リナックスの事だけのblogとして このサイトを作った時の記事です。
(仕事が忙しくてlinux触れなかったので、CADのこととかの記事が
増えてきてしまいましたが・・。)
linux記事を順次移行しようと思っていて、これも忘れていましたー。
3: ユーザー名とパスワードの変更ではなく新規作成がしたい
LINUXでユーザー名とパスワードの設定がやっと出来たので、覚書。
たくさん検索しましたが、「変更方法」の方が圧倒的に多かったので
意外と見つけにくかったので・・このサイトも参考になれば良いなと。
先ず、パスワードの変更方法について。どんな感じかというと
$ passwd [ユーザー名]
# passwd [user]
だそうですが、
なんと、こちとらユーザー名もない状態でした・・ので、新規の登録方法から。
以下、最初に先ず「ROOT」にならなければ話にならなかったので
(それが分かるまでも相当な時間がかかっています。)
ユーザー名なしでもroot権限を取得した方法です。↓
$ sudo su ー 、ユーザ”ー ”のパスワードエントリがありません
↓
$ passwd [user]
(みどり色の文字で表示されている自分の名前を入力するも)
↓
ユーザ〇〇 は存在しません
$ sudo su (- を抜いてみる)
↓
raspberrypi:/home/pi#
・・と、出てきた!やっと「#」になりました。ユーザー名がないのだから、
「sudo su」だけでenter押せばいいだけのこと(大事なので2回)。
ここからユーザの新規作成・パスワードの登録も出来るということになります。
ここで、ユーザー登録から。(※ 見易くするため全角の箇所がありますが、#やスペースは全て半角です!)
# useradd 〇〇(お好きな名前を入力)
# passwd 〇〇(上記と同じ、パスワード設定をしたい名前を)パスワード入力して下さい:〇〇〇〇(お好きなパスワード。入力しても文字は出ません)
〃 再入力して下さい:〇〇〇〇正しく更新されました
これで、ユーザー名とパスワード設定は完了です!お疲れ様です。
初心者の方や、または慣れすぎてしまった方などは、
「ユーザー名の設定がされていない」ということに気付かないかと思います。
私の場合はそうでした。。。
マニュアル本などで、1からの設定を行うと上記のようなことは
おそらく発生しないかと思われますが、ネット検索で無料でどうにかしたい派には
結構ありがちな状態かと。。。
4: linux mintでのssh設定は「sshd不要」だった!と気付いた個人の感想
linux mintでsshの設定をするときは、「sshd」は使わないみたいです!目から鱗です。。
そもそもの発端は、色々なサイトを見ていたら、wordpress ではなくHugoとgithub(gitlab)、netlifyというものを使ってブログを独自ドメインで公開が出来るということ(しかも、サーバー代がかからない、オプション要らない場合などほぼ無料になるので、ドメイン料金のみでブログが運営出来る様になるらしいのです)
だったので、調べていたのですが・・。
プログラム言語(?)などは何でも粗、初心者の私には問題が山積みでした・・。
先ずは、sshが今だ全くわからないのですが、前から「いつかはやらなくては」と、気になっていたし、見よう見まねでコピペでkeyganとかやってみたりしました。
それで混乱してしまったのですが(今もほぼ変わらない)、
ssh_config、sshd_configの違いが・・特に分からず最初は、sshdの存在すら気付かずでした。rootのloginをnoに編集したりするのは、sshではなくsshdのconfigの事だと途中で分かったものの、sshd_configを探しても見つからず困っていました。
何度かsshをインストールしたりするも、一向にsshd_configは出てこないし
仕方がないので、sshd_configのファイルを自分で作成してみました。
configの中の例を載せて下さっているサイト様は少ないので、
見つけ次第に印刷して見比べて、vimとかで何度も何度も編集して
root loginをnoとかも気をつけて・・やっと、それらしきものが出来上がりましたが・・なんと・・
どうやら、linux mint ではsshd_configは必要がなくssh_configだけで良かったっぽいのです・・。
どこかでチラ見した情報で、情報源が不明ですが。
でも、その情報も非常に少ないので困っている人が大勢いるのではないかと思うので、
今回はそのことをシェアさせていただきたく、実は今回その為だけの記事だと言っても過言ではありません。
前置きが長くて申し訳ございませんでした。タイトルに内容は含まれてるので、本文を読む必要もなかったかもしれないですが・・。(汗)
私と同じような初心者の方、上記の事が先ず、知っておいた方が良いです!
他にも、パーミッションとかの問題があるとは思いますが・・また後日改めて調べてみたいと思います。
5: 保護されていない通信を解除する方法
現在はbloggerへ移行しましたが、このサイトは以前はwordpressで
投稿していました。
以下、wordpressを利用していた過去の記事ですが
悩んで調べていた事なので、備忘録として残しています。
- 5-1 確認方法
- 5-2 気づいた経緯
- 5-3 後日、なんとなく分かったこと
- 5-4 以前の記事
全ての「http」を「https」に変更したら、
「保護されていない通信」は、すぐに表示されなくなりました!
確認方法
「コードエディター(HTML・タグ表示)」にして、[shift]+「F」で、「http://」の文字列で検索します。
(・・で、合っていると思いますけど。。)
気付いた理由は・・ある特定の記事だけに「保護されていない通信」がでていたので、その記事を
「コードエディター(HTML・タグ表示)」にして、何が悪いのだろうと隅々までよく確認しました。
すると・・、記事中に貼り付けてある、画像のリンク先・URLがほとんど全部、
httpになっていたのでした。
その記事は画像をたくさん貼り付けていたので、とても面倒でしたが・・
「保護されていない通信」だと、怪しいサイトに見えそうで嫌だったので・・
(実際、自分も調べものをしてたどり着いたサイトが「保護されていないサイト」
って思うと、長居できなくなります)・・がんばって、
全ての「http」を「https」に変更したら、
「保護されていない通信」は、すぐに表示されなくなりました!
それにしても、なんで「http」になっていたのか、さっぱり
なんでか分からないのですが、調べても出てくるのは
逆(http→https)のことばかりです。
もしかすると・・、サイトの引越でhttps→httpになってしまった??
それくらいしか心当たりがなく、他に原因は思いつきません。。。
今回の場合、参考にしていたサイトが古かったので
SSLが必須ではなかったものと思われます。
「参考にしたサイト」などのリンクを貼る時に、参考にしたURLも
気をつける方が良いということです。
もし、ブログをメエ―ル投稿して画像も添付していたら、
その画像がhttp://」になってしまい、「s」が付かない可能性が高いです。
他は、アフィリエイト広告などを張り付けている
ブログのウィジェットに古いリンクが混じったタグが入っている
他は、思いつきませんが、自分の場合はそれらが当て嵌まりました。
参考までに。
このサイト(wordpressのブログを使用していた当時です。他のサイトでも
同じことがありましたが・・)は
サーバーでSSL設定してあって、サイト全体がhttpsの筈なのに、なぜか
「保護されていない通信」って出てくるので、なんでだろ〜と
あれこれ調べましたが・・1つだけ確実に分かりました。
結局のところ、件の自分の記事のURLだけではなく
「記事中」にも、httpsではなく、
「http」という文字が含まれている
・・ということが大きな原因です。
特に古いリンクなどはご注意くださいませ。
通信の危険度で言うと、真ん中なので・・大きな問題ではないのかもですが。。
以下、参考に。↓
・保護された通信
・サイト情報を表示 情報、または保護されていない通信
・危険 保護されていない通信、または危険
6: Rhythmbox|参考・終わり
ついでの話ですが、音楽のプレイヤー「Rhythmbox」というアプリケーションソフトについて。
こちらは、Linux mintインストール時に最初から入っていたと思われます。
最初に音楽のCDを入れた時に、自動的に起動してくれました。
そのため、すぐに使うことになったのですが、読み込んで保存されたファイルの
拡張子が「.ogg」となっていました。
後ほど mp3などへ変換できる方法も調べることになります。
ちなみに、oggファイルを直接クリックしても音楽が再生できました。
その時は、Xplayerというアプリになるみたいです。
(確認方法:ヘルプ→このアプリケーションについて)
ここまで読んで頂きありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。
いつまで経っても自分自身どこまで解ったのか「?」の初心者目線ですが‥。もしも何かしらの参考になれば嬉しく思います。
良かったら気が向いた時にでもまた覗いてやってくださいませ。
よろしくお願い致します。
参考サイト:
サイトの接続が安全かどうかを確認する
https://support.google.com/chrome/answer/95617?visit_id=637362018653729260-3587098048&p=ui_security_indicator&rd=1
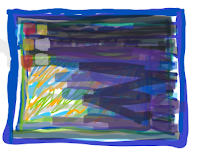



コメント
コメントを投稿
読んでくださって、ありがとうございます。お気軽にコメントして頂けると嬉しいです。返事は90%くらいお返ししますが、めちゃくちゃ遅い場合があります。気長にお待ちください。